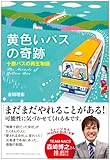子曰。非其鬼而祭之。諂也。見義不爲。無勇也。
子曰わく、其の鬼に非ずして之を祭るは諂いなり。義を見て為さざるは勇無きなり。
【訳】
自分の祭るべき霊でもないものを祭るのは、へつらいだ。行なうべき正義を眼前にしながら、それを行なわないのは勇気がないのだ
************************************************************************************
今回は2つの言葉が出てくるが、前半よりも後半の方が日本では有名である。それはまさに我が国の国民性の表れのように思える。前半は死者に対する態度だが、我が国では死者は敬うという方向である。故に自分の祖先と関係なくても一定の敬意は払う。「バチが当たる」という感覚かもしれない。「祭る」程度にもよるだろうが、「へつらい」とまで言わなくてもいいのではないかという気がする。
それに対して、後半の言葉はとても有名である。寺子屋で武士の子供が一生懸命暗唱しているイメージがあるが、武士道の精神にマッチしていると思う。そしてそれは武士道のみならず、現代に至るまで共感できる感覚である。おそらく、この言葉に反対する人はいないのではないかと思うくらいである。ただ、「実践」となると必ずしもそうではないと思う。
何を持って「義」とするかは議論の余地があるかもしれない。何もいじめられている子を助けるとか、チンピラに絡まれている女性を助けるとか、そういう英雄的なものでなくても、例えば電車の中で席をゆずるようなことも当てはまると思う。身近なところでは、いつも話を聞いてあきれるのは、子供の学校での役員決めである。誰も手を挙げなくて、なかなか決まらないらしい。自分の子供が通う学校なのだから、私ができるものなら喜んで手を挙げるのだが、「面倒だ」と思うのだろう。「勇」は何も勇気の意味だけでなく、「心意気」の意味もあると解したいのである。
また、仕事でいつも感じることだが、「自分の意見を言う」というのもこれに当たると思う。会社全体での動きについて、人は誰でも多少なりとも自分の意見は持っているだろう。社長が、あるいは上司がやろうとしていることに対し、「違うのではないか」と思ったらそれをきちんと言うのもこれに当たると思う。現に中小企業ながら我が社でも自分の意見を言わない(言えない)人がいる。たとえ反対でもそれに対して意見は言わず、黙って従うのである。そして後で、「自分はいかがかと思う」とこそっと呟くのである。そう思うのなら、なぜその時言わないのか。まさに「勇なきなり」ではないかと思う。
あるいは、先の役員決めと一緒で、「面倒だ」と思うのかもしれない。社長の出した方針に対し、反対意見を出せばまず議論となる。自分なりの意見をまとめて話すのは結構大変だし、その結果意見が通っても、「ではお前がやれ」と言われたらそれを受けないといけない。私はいつもそう言う覚悟を持って発言しているし、別にそれが苦になるわけではないのであるが(まぁたまにめんどくさい時はあえて黙っている)、人によってはそれが苦になると言うのかもしれない。
「めんどくさい」と思うから言わないというのも、ある意味やむを得ないケースもある。人によって仕事に対する姿勢は様々だし、「ほどほどにやっていたい」という人もそれはいるだろう。責任のある地位についていればそう言うことは許されないが、地位によっては仕方ない人もいるだろう。社長に近い人であれば、そういう意識を持っていたいものであるし、それこそ「勇」なのかもしれない。
自分の身の回りでは、「義」と呼べるのは、仕事ぐらいなものかもしれない。それと「誰かがやらなければならない何か」というイメージだろうか。あえてわざわざ面倒に思う心を克服してやることこそが、私にとっての「義」であるという気がする。何も眦を決して死にそうな覚悟で臨むような大げさなことではなく、ほんの身近な日常にある小さな「義」を見て為すようでありたいと思うのである・・・