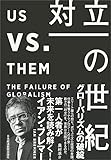先日のこと、仕事でちょっとした不手際があった。性格的にあまり人の細かい失敗を責めるのは合っていないのであるが、下手をするとお客さんにも迷惑をかける話なので、責任者に厳重注意を申し入れた。それと合わせて、その元となった仕事を翌日中に終わらせるように依頼した。2日あれば十分終わるだろうとの読みであり、それで十分だったからである。
その責任者は、たぶん腹を立てたのだと思う。と言っても私の言うことのほうが正論なので文句も言えない。渋々と頭を下げて承知してくれた。そしてその日のうちに残業してその仕事を終わらせてしまった。残業すれば余計なコストがかかるということは抜きにして、その日のうちに終わらせたというのは、その人の「意地」だろう。「反骨心」とも言えるかもしれない。こういう「意地」は個人的に大好きである。
もしも立場が違い、私がその責任者の立場だったら同じことをしただろうと思う。その仕事は、実はその人の部下のしたことであったのだが、責任者としてはそれを言い訳にはできない。その日のうちに残業して終わらせたのは、自分の腹立ち紛れということもあるし、原因を作った部下に対する教育的指導の意味もあるだろう。いずれにせよ、翌日まで使ってゆっくり仕上げるのと比べると、その意味は大きいと思う。
こういう「意地」ってとても大事だと個人的には思う。それは「悔しい」という気持ちの現れであり、そしてそういう「悔しい」気持ちこそが進歩をもたらすものだと思うからである。それはスポーツでも仕事でも相通じるものだと思う。逆にそういう悔しいという気持ちや反骨心とも言える「意地」を持たない人は、迫力に欠けるし、スポーツにおいても仕事においても何かを成し遂げるということもない気がする。
これまでの人生を振り返ってみると、そういう「意地」のない人というものは確かにいる。そういう人は挑戦をしない。私は高校3年時、担任の先生との進路面談で、志望大学には受からないと言われた。それは結果的にその通りであったが、私は自分の意思を通して浪人し、猛勉強して再度受験し、そして合格した。「意地」を持たない人は、合格しないと言われればそうかと挑戦をやめてしまうだろう。
女性を口説くのだって、ちょっと声をかけてうまくいきそうなら告白するというのでは、(よほどのイケメンであれば別だが)女性なんて口説けないだろう。断られても再アタックできるのは「意地(この場合は意気地か)」があるからだろう。最近、独身比率が高いのは、男の側にこの意地のある男が少なくなっているからというのも一因であるような気がする。そんな人は、先の仕事の例でいけばたっぷり期限まで時間をかけてゆっくり仕上げるに違いない。
一緒に仕事をする立場としては、そういう意地のある人に対しては絶対的な信頼感を置ける。なぜなら意地でも自分の仕事には責任を持って仕上げるからである。しかし、言われてものほほんとしている(ように見える人も含む)人には絶対的な信頼感は置けない。仕事をお願いしても最後まできちんとやってくれるか目を離さずにいないといけない。その信頼感の差は比較できないほど大きい。当然、責任ある仕事など任せられないであろう。
そういう意地の話になると、高校生の時のラグビーの夏合宿を思い出す。午前午後とハードな練習を課される日々。ある時、グラウンドを何周もランパス(パスしながらのランニング)で回らされた時のこと、コーチがキャプテンであった私に「もう無理か?」と聞いてきた。正直言ってその時点までいつストップの声をかけてくれるかと待っていたのだが、それを聞いた瞬間、私は「まだまだです」と答えていた(後でチームメイトに大ブーイングを浴びたのは言うまでもない)。そういう「意地」がもうその時の私には存在していたのである。
そういう意地は、いつどのようにして身につくのであろうか。意地の片鱗もあるように見えない人を見ていてそう思う。そういう人は、気力の点においても流されやすい無気力さを感じる。困難に際しても「仕方ないんじゃない」で終わらせてしまうし、ちょっとハードルが高そうだと思うと諦めてしまう。実際にそういう人を見ていると、つくづく意地のあるなしで人生は大きく変わってしまうだろうなと思ってしまう。
自分には(変な意地かもしれないが)、そんな意地があってよかったと思うのである・・・
【今週の読書】